これは私が1997年12月18日に執筆した物語を記録するものである。
登場人物
わにたろう
わに子
わにみ(おかあさん)
わにさぶろう(おとうさん)
ちゅん(すずめ)
スーパーきょうわくわるわるくじら王

わにたろうとわに子のぼうけん
「わにたろうくんおきて」
わに子はぼうけんのすきな女のわにです。
「またぼうけんか。」
わにたろうはねむそうに言いました。
「わるい。」
わに子がおこって言いました。
「そうだ海できょうそうしない。」
わに子がたずねました。
「うん。いくよ。」
わにたろうが答えました。
「じゃあ行こう。」
わに子がうれしそうに言いました。
二人は北のしままできょうそうしましたが、わにたろうがとちゅうで、
「もうおよげないよう。」
となきました。
わに子は
「もう、しょうがないな。」
といってせなかにのせました。
なんとかしままでつきました。
二人はつかれたのでねむってしまいました。
「わに子なんか音しない。」
わにたろうが言いました。
「え、あ火山だよ。」

二人はおきました。
二人はいそいで南のしまにいこうとしました。
二人は海に入っておよぎました。
南のしまにつきました。
「あれ、火山は、ゆめだったの。」
二人はいっしょに言いました。
「でもおよげたじゃん。」
わに子が言いました。
「まあね。」
わにたろうがじまんそうに言いました。
「あ、はちのすふんじゃった。」
とわにたろうが言いました。

二人はおおいそぎでにげ回りました。
はちはにげました。でも、
「いたいよー。」
わにたろうがさされてしまいました。
がすぐなおりました。
そこへすずめのちゅんがきました。
「いっしょにあそばない。」
わに子が言いました。
「いいよ。」
ちゅんが言いました。
「遠足にいくんじゃなかったの。」
「ちゅうしになったの。」
「じゃんけんしない。」
「でももうおそいから帰るよ。」
ちゅんが言いました。
「バイバイ。」
わに子とわにたろうが言いました。
二人はふねにのって家に帰りました。


「今日はすごいぼうけんだったね。」
わに子が言いました。
「ねえ、おかあさん。」
わに子が言いました。
「なんだい。」
おかあさんのわにみが言いました。
「あのね 今日、すごいぼうけんしたんだよ。」
わにたろうが言いました。

「もう わたしがいおうとしたのに。」
わに子がおこりました。
「けんかしちゃだめよ。」
とおかあさんにいわれ
「はい。」
と二人はちいさいこえで言いました。
二人は家ではなく外でまたねてしまいました。

「ねえ、海にもぐらない。」
わにたろうは言いました。
「うん、いいよ。」
わに子が言いました。
二人はゆめのなかで海にもぐりました。
「ねえねえなにか光ってるよ、いってみない。」
「うんそうだね」
「あっおかねだ。」
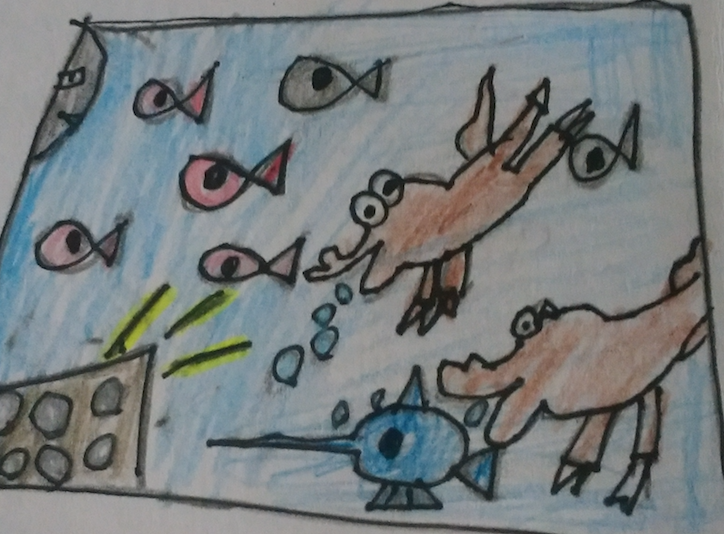
二人はよろこんだけどそのとき
「うわー。」
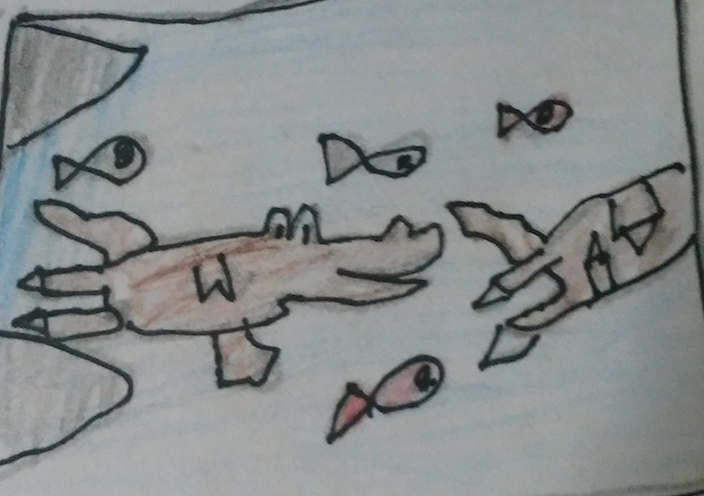
二人はスーパーきょうわくわるわるくじら王にくわれてしまいました。
二人はおなかのなかでないているとさかなたちがきました。

「どうしたんだい、スーパーきょうわくわるわるくじら王にたべられたのかい。」
わにたろうが言いました。
「うんそうなんだよ。」
さかなたちもないてしまいました。
「そうだ、計画をた(て)るんだ。」
さかなたちとわに子とわにたろうは計画をたてています。

「まずしんでいるさかなをつなげてくじらのおなかをたたけばいいと思うけど。」
わにたろうがしんけんになって言いました。
「どうやってつなげるの。」
わに子が言いました。
みんな考えていると
「そうだ、くじらのよだれでひっつけたらいいんだよ。」
さかなたちが言いました。
みんな一づつつくりました。
たたいてみるとまるいあながあいてみんなあなからでると
「やったー。」
とみんな言いましたが、そこはまだくじらのはのところでした。
みんながっかりしたけどつぎのさくせんをきめました。
「わにたろうくんがくじらのはをかんではをおったらいいと思うけど。」
とさかなたちが言いました。
みんなでれました。その時二人はゆめからおきました。
「またゆめだったのか」
二人はいっしょに言いました。
そのときおとうさんのわにさぶろうがしごとから帰ってきて
「こらなにしてんの。」
とおこられました。
「ごめんなさい。」
二人はおとうさんにいってわらいながら帰りました。
